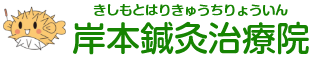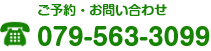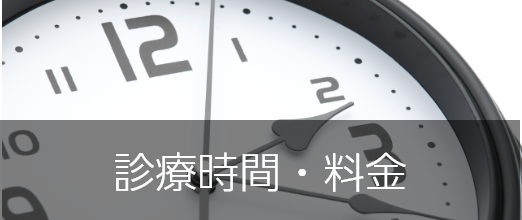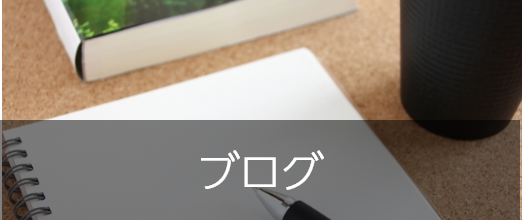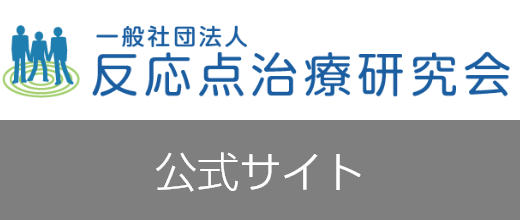お灸をすえるってどういうこと?
2025年10月10日、掲載
お灸のことを関西では「やいと」とも言います。
地方によって呼び方は違うこともあるそうです。
奥の細道で知られる松尾芭蕉もお灸をして体調を整えていたと言われています。
今回はそんなお灸について話そうと思います。
悪い事をした者への罰則として「お灸をすえる」という表現がありますね。
「○○政権にはきついお灸をすえないといけない!」
こんな使い方を耳にすることがありますね。
子供の頃に悪さをしたら
「やいとするで!」と言われたこともありました。
実際に親にされたことはなかったですが。
ただ、お灸はそんなに辛いものではありません。
また罰則でもありません。
むしろ逆で、体の元気を出すためにお灸は有効です。
当院でもお灸は使っています。
昔ながらの艾(もぐさ)を皮膚の上に置くやり方もします。
ただ今では皮膚に直接艾を置いて燃やすのではなく、間接的におこなうお灸があります。
代表的なものに「せんねんきゅう」があります。
台座の上に紙巻にした艾をつけて皮膚の上で燃やします。
台座は燃えないので間接的に熱刺激を与えられます。
どちらのタイプも使います。
お灸をするには「きゅう師」の免許が必要です。
多くは、「はり師」の免許と両方の資格を持っていることが多いですね。
市販のせんねんきゅうを家庭でおこなうのは一般の方でもいいようですね。
薬局やドラッグストアで売っていますからね。
昔、祖父が大きな艾(もぐさ)を背中等にしているのを見ていました。
背中には父がすえていました。
結構大きな艾が背中で燃えきっていました。
今思うとかなり熱かったと思います。
でも、そんなに熱いお灸でなくても問題ないですよ。
少しチカッとするか、ほんのり温かい位でもいいのです。
当院ではもちろん、基本的には心地良い位のお灸をおこないます。
ご安心下さい。
私はその祖父が亡くなってから鍼灸師に転身しました。
その頃、祖父はまさか孫が鍼灸師になるとは思っていなかったでしょう。
2025.10.10