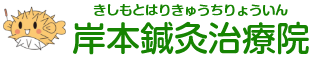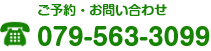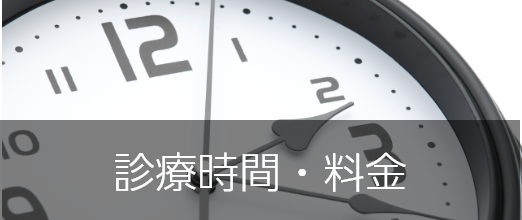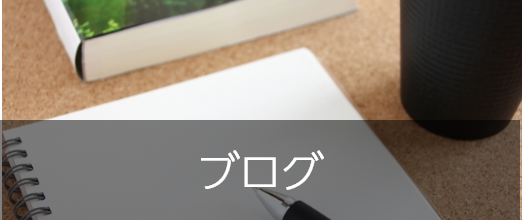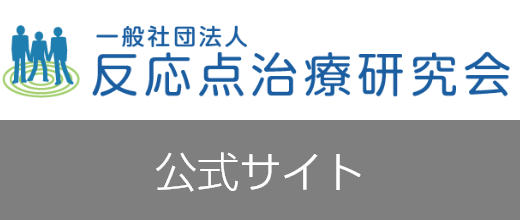当院に新たに来られる症状の中で坐骨神経痛の方は少なくありません。
医師に診断された方以外に、自分で調べて坐骨神経痛だと判断している方もおられます。
腰、臀部、ふともも、すねやふくらはぎに痛みやしびれ感が出ることが多いようです。
坐骨神経痛という病名からがっかりされている方もおられます。
大変な病気になってしまって辛い気持ちになられているのでしょう。
ただ、ここでお伝えしたいのは、「あきらめてしまう必要はないですよ」
ということです。
確かに辛い症状ですが、筋肉の緊張に注目して施術すれば改善する方が多いと感じます。「神経のことだから治りにくいだろうな」そんな印象をお持ちでしょうが、注目すべきは筋肉だと考えています。
筋繊維の緊張によっていびつなひきつりのようなものができます。
この状態を痛みのアンテナがキャッチします。
そうすると痛みの神経が興奮して、その場所が痛いことを脳に伝えます。
そういう仕組みから考えますと、筋肉、筋繊維の緊張を緩和することが必要なのです。
私は神経そのものがつぶれる、または変になっているとは思いません。
筋肉の問題だと考えます。
そしてこの筋肉は坐骨神経痛の場合は、泌尿器系と生殖器系が関連していると考えています。
したがって当院では泌尿器系の器官、生殖器の反応点と腰や臀部、ふとももやふくらはぎ、すねの筋肉に施術していきます。
よろしければこちらもご確認下さい。
当院ホームページ内 坐骨神経痛
https://kishimoto-harikyu.com/zakotusinkeitu/
2025.6.6
坐骨神経痛だと言われてもあきらめない!を確認する
顎関節症(がくかんせつしょう)でお困りの方も案外多いと思います。
口を開ける時に痛みが出る、口が開けにくい、という症状が有名です。
顎(あご)の関節を構成する咀嚼筋(そしゃくきん)や関節円板、靭帯に問題があると言われています。
私は中でも咀嚼筋の緊張に最も注目しています。
筋肉に強いコリの状態が発生すると、結果口が開けにくくなります。
また痛みも出てしまいます。
噛み合わせの改善のために歯医者さんに通う方も多いでしょう。
噛み合わせが悪くなるのは筋肉の問題でしょう。
咀嚼筋の緊張状態が左右で違えば、噛み合わせも変化しますからね。
歯や歯茎に問題があると歯医者さんに行きますね。
そんな時これらの筋肉も緊張が促される可能性は十分にあります。
また精神的なストレスによって「食いしばり」「歯ぎしり」が起きます。
この場合も筋肉がガチガチに固まるかもしれません。
筋肉の緊張を緩和することがとても大切です。
こめかみのところにある側頭筋が緊張すると頭痛つながります。
片頭痛の場合、当院では必ずここは施術します。
よろしければこちらもご確認下さい。
当院ホームページ内 顎関節症
https://kishimoto-harikyu.com/gakukansetsu/
2025.5.26
顎関節症について考えてみようを確認する
紫外線が強い季節になってきました。
これからがさらに強くなっていく季節ですね。
この紫外線についてちょっとお話しします。
よくご存じの方もいらっしゃるでしょうけど復習の意味でお付き合いいただければと思います。
光の中で見えるものを可視光線と言います。
赤、橙、黄、緑、青、紫 と波長の長さの順番になっています。
そうです、虹の色ですね。
赤より波長の長いものが赤外線、紫よりも短いものが紫外線ですね。
この紫外線ですが、やはり気を付けたいものです。
昔は、日焼けするのはいいことで、良く焼けた子は元気な子のイメージでした。
しかし今ではシミの原因になる、皮膚へのダメージが大きい等と良くないことが知られるようになりました。
きちんと日焼け対策を取りたいものですね。
日焼けの話日差しに関連して、ここで紹介しておきたいお話があります。
当院の患者さんのお話ですが、以前こんな話がありました。
「天気のいい日に屋外で作業をしていたら顔が火傷のようになりました」
「こんなことになったのは初めてです」
数日経って、落ち着いたとは言え、赤くなっていました。
もしかすると・・・と思い、服用しているお薬を尋ねました。
やはりそうかもしれないと思いました。
ネットで検索して確認してみると、お薬の副作用のようです。
光線過敏症と言って炎症、かゆみなどが出ます。
医師にきちんと伝えて、薬の変更などの相談をしてくるようにと伝えました。
後日、病院で薬を変えてもらったとのことでした。
光線過敏症の出る可能性のあるお薬は何種類もあります。
思い当たる方は医師にきちんと相談して下さいね。
私の前職は病院周りの薬の営業でした。
こんなところでちょっと役立ちました。
2025.5.23
日焼けには注意が必要ですよを確認する
兵庫県三田市より坐骨神経痛にてご来院
Aさん 初来院時50歳代 女性
坐骨神経痛の症状で悩んでいた。
・腰、臀部の痛み
・ふとももの外側と裏の痛み
・ふくらはぎの痛み
・足のしびれ
無理をしてでもやらないといけない状況とのこと。
自営業のため休んでしまう訳にはいかない。
症状が多く、かつ重い。
足腰、臀部に症状がでるということは泌尿器生殖器の反応点を確認することになる。
案の定、これらに顕著な反応点が見られた。
症状を安定させるために継続が必要だ。
生殖器の反応点や泌尿器の反応点には毎回、お灸をおこなった。
その上で腰、尻、ふともも、ふくらはぎ等にも鍼刺激を加えていく。
初日の施術が終わった後に改善を感じた様子だった。
「ズボンが履きやすい」とのことだった。
2回目は二日後だった。
初回の施術で足のしびれは消失したと報告があった。
しかしその他の部分は改善しているが痛みは消えてはいない。
この日も泌尿器生殖器の反応点と各部の筋肉反応点への鍼灸刺激をおこなった。
これ以降しばらく施術の間隔をあまり空けることなく来院された。
症状は改善していったが夜になると辛さが出る等なかなかの重症だった。
その後数カ月頑張って通院して症状は安定していった。
ある程度の頻度で通院することが理想だがしばらく来られなくなった。
その後は思い出したかのように来られることがある。
辛くなったら来るという感じだ。
(感想)
やる時には徹底して通院する方です。
理想は日頃から体調管理しながら元気に過ごしてもらいたいものです。
かなりつらい状態でも明るく振舞う方です。
家族にも悟られず無理してしまうのではないかと心配になる方です。
(参考)
当ホームページ内 坐骨神経痛のページ
https://kishimoto-harikyu.com/zakotusinkeitu/
2025.5.3
坐骨神経痛の施術例 1を確認する
「春眠暁を覚えず」
(春になるとよく眠れて朝になっても気付かずついつい寝過ごしてしまう)
こんな感じの意味ですが、この季節にはよく聞く言葉ですね。
しかし不眠症の方は春になってもよく眠れないものです。
眠れないということはとても辛いことなのです。
・寝つきが悪い
・途中で目が覚める
・眠りが浅い
当てはまる方も結構多いかもしれません。
様々な病気や精神疾患、ストレスなどが関係していると言われています。
個々の病気などによって違いはあると思いますが、
大雑把に言ってしまうと、身体がゆっくり休む状態にならないということでしょう。
炎症や痛み、内臓の疲れや病気が交感神経を過剰に興奮させます。
結果精神も昂るのでしょう。
つまり、これらの信号が脳を昼間の活動期のような状態にしてしまっているとも言えます。
このような苦痛の信号を減らすことが大切だと思います。
・大きな原因となっていると思われる部分を確認
・そこを重点的に施術、刺激
・その他の反応点もチェックと刺激(全身への施術)
眠るための「身体の環境づくり」をすることが必要だと考えています。
2025.4.29
不眠症は大変ですねを確認する
病気や身体の不調が出ると多くの方が病院に行きます。
どんな診断が出るのかな、原因は何だろうかと不安になるものです。
ドキドキして検査結果を待つこともあるでしょう。
そんな時「検査結果は特に異常はなし」と言われたらホッと一安心でしょう。
それでも、辛い症状があるのに異常はないのかな?と心配になる方も多いはずです。
「こんなに辛いのに異常なしなんておかしい」と思うかもしれません。
当院でその不満を打ち明ける方もいらっしゃいます。
検査結果と自覚症状が一致しない場合ですね。
自分の辛さを理解されないことはとても歯痒いのでしょう。
ご本人の辛さはその方の主観ですから、症状と一致しないこともある。
確かにそうかもしれません。
ただ血液検査等でしっかりとその時の状態を確認できる検査もたくさんあります。
しかし、画像診断(レントゲンやCT等)の場合、全てがわかるわけではありません。
例えば脚の痛み、腰痛、膝の痛み、肩の痛み、五十肩などは多くの場合、筋肉の痛みです。
筋肉の状態を細かく捉えるのは難しいと思われます。
したがって画像だけでは判断できないのだろうと思います。
そんな時に当院では「反応点治療」という手法で施術します。
・筋肉の形に沿って出てくる筋肉の反応点
・その筋肉を緊張させた可能性のある内臓器官の反応点
これらを検討しながら施術します。
改善のための方法が見つかることが多くあるのです。
2025.3.25
検査結果は異状なしを確認する
三叉神経は顔面の痛みを脳に伝える神経です。
顔面に痛みがあるということは、痛みを感じさせる発信源があるということです。
当たり前のことを言うなと指摘がありそうですね。
したがって三叉神経痛の場合皮膚、その下の組織、筋肉などを確認していきます。
よく三叉神経への物理的な力が加わることによる障害だというような記述を目にします。
しかしそうでしょうか?
いつもこの手の記述には疑問を感じてしまいます。
なぜならば、神経が障害されてしまったら痛みを伝達できないからです。
その痛みを感じているのですから神経そのものは正常だと考えます。
つまり神経の末端にある受容器(アンテナ)の先に痛みの原因があると考える方が妥当だと思います。
顔面神経痛という表現もありますが、顔面神経は運動にかかわる神経ですので、顔面部の痛みは三叉神経痛と呼ぶ方が正確だと思います。
顔面神経麻痺はどう考えるのか
上で書いた三叉神経痛を考える時に、顔面神経麻痺と混同されている可能性があると思うことがあります。
確かに、顔面神経麻痺の場合は神経の障害です。
何か物理的な力が加わって神経が障害を受けたのでしょう。
結果として顔面の筋肉等を動かす神経が麻痺しているので動きません。
当院での施術は以下のように考えています。
三叉神経痛の場合は顔面部やその周囲の緊張や痛みの発信源を探します。
そしてその部分の回復を図っていきます。
顔面神経麻痺の場合は障害された神経の回復が早くなることを目指します。
2024.3.1
三叉神経痛について考えてみようを確認する
兵庫県三田市よりめまいと腰痛にてご来院
Sさん 初来院時80歳代 女性
最初は腰痛を訴えて来院された。
子供さんに大切にされている方で、毎回送迎してもらっていた。
その他頻尿や腹部の不調があるとのことだった。
主訴の腰痛は膀胱や子宮の粘膜に炎症があるからだと考えた。
これら泌尿器、生殖器の反応点にお灸を行い改善を図った。
少しずつコンディションも良くなっていった。
数回来られた後のある日、いつもよりも内耳の反応点が顕著に見られた。
初回から内耳に反応点は見られたが、その時はいつもより状態が良くなかった。
めまいが出ていないか?と質問したら驚いたようだった。
実は時々めまいが出て、日によってはかなりひどくなるとのこと。
めまいには内耳の反応点に刺激することを説明し、施術を始めた。
するとなぜめまいがあることが分かったのかと不思議がられた。
そしてホッとしたように話してくれた。
めまいがするのは脳に問題があって死が近づいているからだと思っていたとのことだった。
子供さんや家族に心配をかけると思い、誰にも言えずに過ごしていた。
しかし、脳ではなく耳の問題ではないかと思えたことで気持ちが楽になった。
そして、それだけでかなり元気な顔になった。
その後もめまいの施術を継続した。
状態も安定し、元気になられてこちらもうれしかった。
それ以来この方は私に向かって手を合わせt拝んで帰る方だった。
仏でも神でもない私に手を合わすのは恥ずかしかった。
(感想)
めまいは脳が悪いからだと思い悩んでいる方がいると気づかされた。
この方の場合のように良くなる可能性があると分かると元気が出るものです。
簡単にあきらめずにお手当してみる価値はあると感じています。
(参考)
当ホームページ内 めまいのページ
https://kishimoto-harikyu.com/memai/
2025.1.27
めまいの施術例 1を確認する
手がしびれる。
足がしびれる。
脚がしびれる。
多くの方がしびれを経験しています。
正座を長時間した後にもしびれを感じます。
平気な方もいるかもしれませんが、私は結構しびれます。
お坊さんは平気なのでしょうか。
このしびれは皮膚がピリピリとしている感じとでも表現しましょう。
患者の方と話していると「しびれがあります」「しびれています」等と表現されます。
開院して間もない頃はしびれ感とはこの、皮膚のピリピリ感のことだと判断していました。
しかし長年話していますと、患者さんの言う「しびれ」はこのピリピリ感だけではないことが分かりました。気道の炎症があると敏感になります。
他の「しびれ」とは何のこと?と思う方もいらっしゃいますね。
実は鈍痛、ズーンと響くような痛みのような感じ、重だるさ、えぐみとでも言いましょうか、この手の感覚も「しびれ」と表現される方がいらっしゃいます。
しかも一定の割合でいらっしゃいます。
どちらも辛い症状です。そうならば管理しながら過ごすことが必要ですね。
そしてどちらも筋肉の緊張が関係していそうです。
筋肉の緊張へのアプローチが必要になりそうですね。
その上でピリピリ感のしびれは特に皮膚、筋膜に着目しないといけないと思います。
感覚としてはちょっと違うものですが、表現としては同じ「しびれ」が使われることがある。
開院間もない頃はしばらく気づきませんでした。
どちらが正しい、正しくないはどうでもいいですがね。
いずれの場合も辛い症状です。
我慢せずにお手当てしてはいかがでしょうか。
当院ホームページ、しびれ感のページです。
よかったらこちらもご覧下さい。
https://kishimoto-harikyu.com/page-1271/
2025.1.20
しびれ感という表現についてを確認する
今年もあとわずかになってきました。
多くの方がお休みに入ったとこでしょうか。
年末年始もお仕事の方もいらっしゃることでしょう。
最近のニュースでも盛んに報道されていますがインフルエンザが大流行しています。
空気も乾燥していますから流行る要素も整っています。
人混みに行くと無事で済むとは限りません。
そうは言っても人とたくさん会う時期ですね。
そんな中でも、なんとか風邪引きを回避したいものです。
・休暇中とは言えあまり無茶な生活をしない
・室内の湿度を保つ
・外出時はキャンディやガムで喉の乾燥を防ぐ
こんな感じでしょうかね。
手洗い等できることはきちんと行いましょう。
完全にウィルスや菌を避けることは不可能です。その上で気管支の反応点をお手当するこだからこそ、できる対策はおこなうことが大切です。
そして一番は大事ななのは元気な体を維持することですね。
抵抗力のある状態で過ごして風邪をはね返しましょう。
2024.12.29
年末年始、それ以降も風邪引きに気をつけて!を確認する
おすすめコンテンツ